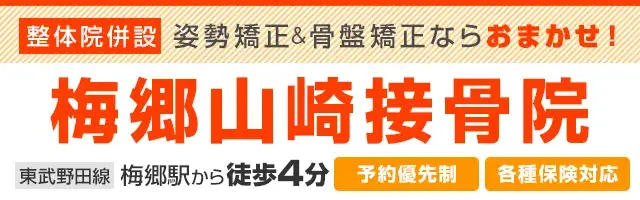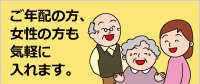オスグッド

こんなお悩みはありませんか?

膝下の突起部分(脛骨粗面)の痛みや腫れが見られる
膝の下の骨が盛り上がり、押すと痛みが強くなることがある
ジャンプやダッシュ、キックなどの動作で痛みが悪化する
長時間の休息後や運動後に特に痛みを感じることがある
赤く腫れたり、ほてりや熱感を感じることがある
オスグットについて知っておくべきこと

成長期特有の症状
主に10~15歳頃の成長期の子どもに発生し、骨の成長と筋肉・腱のバランスの不均衡が主な原因です。成長が止まると、自然に症状が軽減することが多いです。
スポーツをする子どもに多い
サッカー、バスケットボール、陸上競技など、膝に負担がかかる運動をする子どもに特に多く見られます。
膝の下が痛む
膝の少し下(脛骨粗面)が押すと痛む、または運動時にズキズキとした痛みを感じることがあります。
腫れや突起が現れる
膝下の骨が目立って大きくなることがあります。これは脛骨粗面が成長期の負荷で突出するためです。
片膝または両膝に症状が現れる
片方の膝だけに症状が出る場合もあれば、両膝に症状が現れる場合もあります。
症状の現れ方は?

• 膝の下の軽い痛み
初期段階では、膝下の脛骨粗面に軽い痛みや違和感を感じることがあります。特に運動後や運動中に痛みが強くなることが多いです。
• 押すと痛む
痛みは膝の下の骨(脛骨粗面)を指で押したときに特に強く感じることがあります。
症状が進行すると
• 痛みの悪化
運動を続けると、痛みが徐々に強くなり、日常生活でも痛みを感じることがある場合があります。
• 腫れ
膝下が腫れてくることがあります。この腫れは脛骨粗面に炎症が起きているためです。
• 突起の形成
膝の下の骨が目立って突き出ることがあります。これは脛骨粗面の成長板が負荷によって刺激されるためです。
その他の原因は?

• 体型や姿勢
O脚やX脚などの膝のアライメント異常がある場合、膝への負担が偏ることがあります。
• 過度な運動量
休息を取らずに激しい運動を繰り返すことで、症状が発生したり、悪化したりする可能性があります。
• 遺伝的要素
家族にオスグッド病を経験した人がいる場合、同様の症状が出るリスクが高くなることがあります。
• 下腿の筋肉の硬さ
大腿四頭筋やハムストリングスに硬さがあると、脛骨粗面や膝に負担が増える可能性があります。その結果、オスグッドの症状が悪化することが考えられます。
以上のことから、姿勢の維持や柔軟性を向上させることは非常に重要です。
オスグットを放置するとどうなる?

痛みの悪化
• 慢性的な痛み
運動を続けて膝に負担をかけると、痛みが慢性化することがあります。運動時だけでなく、日常生活(階段の昇り降りや歩行)でも痛みが生じることがあります。
• 活動の制限
痛みが強くなると、好きなスポーツや日常生活での活動が制限される可能性があります。
膝下の骨の変形
• 脛骨粗面の突出
オスグッド病を放置して過度に負荷をかけると、膝下の脛骨粗面(骨の突起部分)が大きく突出したまま固まることがあります。これが目立つと、見た目が気になる場合もあります。
• 骨の成長異常
稀に、成長板に過剰なストレスがかかることで骨の成長が不完全になることがあります。
当院の施術方法について

当院でオスグッドに有効な施術として、下半身の筋膜ストレッチ、EMS、全身矯正があります。
下半身の筋膜ストレッチを行うことにより、筋肉の柔軟性を高めることができます。大腿四頭筋やハムストリングスが硬くなると、脛骨粗面や膝に負担をかけやすくなり、痛みが生じることがあります。また、姿勢の悪さにも関与するため、柔軟性を高めることが重要です。
EMSでは、固くなった筋肉を電気的に緩めることができます。これにより、筋肉の緊張を軽減できることが期待できます。
全身骨格矯正は、下半身や上半身、骨盤の歪みを矯正する施術です。骨盤や全身に歪みがあると、普段から腰や膝に負担をかけやすくなり、オスグッドの痛みを悪化させてしまうことがあります。そのため、正しい姿勢を保つことは、症状の軽減が期待できる重要なポイントです。
改善していく上でのポイント

1. 膝への負担を軽減する
• 運動量を調整する
痛みがある場合は、膝に負担のかかる運動(ジャンプやダッシュなど)を一時的に中止または軽減します。
例:運動を完全にやめる必要はありませんが、低負荷の活動(ウォーキング、スイミングなど)を選ぶことが推奨されます。
• 休息を取る
痛みが強いときは十分な休息を取り、膝の炎症が落ち着くのを待つことが大切です。
2. ストレッチで筋肉の柔軟性を高める
• 大腿四頭筋(太ももの前側)のストレッチ
太ももの前側の筋肉が硬くなると膝への負担が増えるため、毎日ストレッチを行うことが重要です。
• 適切な筋力バランスを保つ
膝周りの筋肉を鍛えることで、膝への負担を軽減できます。ただし、痛みがあるときは無理をせず、軽いトレーニングから始めることが大切です。
監修

梅郷山崎接骨院 院長
出身地:北海道札幌市
趣味・特技:古着、サウナ